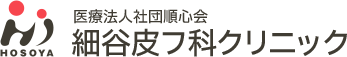水虫
水虫は5人に1人はもっているといわれるくらい多い病気です。
常識かもしれませんが、白癬菌(みずむしきん)の寄生する場所によって呼び名が違います。
足にできた場合は水虫、体にできた場合はたむし、またにできた場合はいんきんたむし、頭にできた場合はしらくもと呼ばれています。
白癬菌は皮膚の表面の角質をえさに、全身のいたるところに発症し、放っておくと確実に拡大していきます。
湿気と適度な高温を好むので足、また、わきの下などは出やすい部位です。
料理人などでは、よく水を使うために手に水虫が発症することも多いです。
水虫の種類
足にできる水虫は大きく分けると3種類あります
ゆびの間の皮膚がつけ根からかさついてむけたり、ふやけて白くなったり、赤くただれるのが趾間型(しかんがた)、土踏まずからゆびの裏側を中心に小さな水ぶくれができる小水疱型、足の裏が全体にかさかさとして白っぽくなったり、かかとが厚くなりひび割れたりするのが角質増殖型です。
小水疱型は梅雨前頃から真夏にかけて爆発的に増えてきます。
かゆみは感じない人もいれば、かきむしるほどかゆい人もいて個人差があるようです。
かゆくないから水虫ではないというのは大間違いです。
皮がむけている部分の皮膚をピンセットでとり、顕微鏡で白癬菌(みずむしきん)がいるかどうか調べることで診断が確定します。
-
小水疱型

-
趾間型(しかんがた)

-
角質増殖型

-
手の水虫

治療方法
あきらめずに根気良くカビを殺す外用薬(抗真菌剤)を最低3ヶ月は塗り続けましょう。
ただしかかとがかたくガサガサになる角質増殖型の場合、何年も治らずに再発を繰り返す場合や爪が白く濁り厚くなってしまうような爪水虫を併発している場合は水虫菌(白癬菌)をやっつける飲み薬(抗真菌剤)も必要です。
家族の中に誰か一人でも水虫の人がいるとその人が感染源となり家族中に拡がります。
そのために最近は両親や祖父母が感染源となり、幼稚園児までもが水虫になり来院するケースが増えてきています。
そこらじゅうに菌をまき散らさないように、また菌の住家になる角質を厚くしないように、きちんと薬をつけて、家の中では薄手の綿の靴下を履くようにしましょう。履く靴はできたら通気性の良いものを選んで下さい。
爪水虫(爪白癬=つめはくせん)
足の水虫を長い間放っておくと爪の中にまで水虫菌(白癬菌)が入り込みます。
爪が白く濁り、厚く肥厚し変形し、最悪の場合は爪がなくなる(爪欠損)ことがあります。
爪の水虫をしっかりと治さないと、いくら皮膚に外用薬を塗って良くなっても、靴下の中で爪がぼろぼろとはげ落ち、皮膚に水虫菌が逆戻りしてまた水虫になってしまいます。
治療薬
水虫菌を殺す薬を服用します。現在、グリセオフルビン、テルビナフィン、イトラコナゾールの3剤が使われています。
個人差がありますが足の爪の場合、テルビナフィンの内服により爪の伸びの速い人なら約5~6ヶ月、遅い人でも約1年半の間、抗真菌剤の内服を続けることにより、白癬菌に侵された汚い爪が少しずつおしだされ新しいきれいな爪に生え替わっていきます。
あきらめないで根気良く治療しましょう。
-
54歳男性

-
内服開始10ヶ月後

-
74歳男性

-
内服開始10ヶ月後

アクセス
-
電車でお越しの方
東京メトロ東西線「葛西」駅より徒歩30秒
-
〒134-0083
東京都江戸川区中葛西3-37-1 ファーストアベニュー2F
※電話応対は最終診療時間の30分前まで